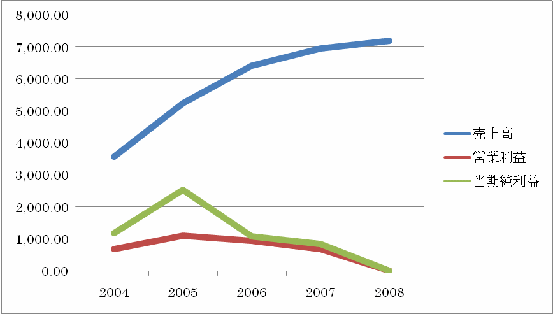
�C���^�[�l�b�g��Ƃ̔�r�o�ϕ���
�| Yahoo! vs Google �|
2010�N1��15��
���[�~3�N �i2008�N4��������)
�ɓ��G���@���䍂�@���c�m��
�@���q�T��@��㏫(��)�@������
�c������@�z�R�ÜA�@�璼�l(��)
���������@��������@�R�����l
(������������, ���͎��s��)
�ڎ�
II. �{�v���W�F�N�g�̂˂炢 �|�Ȃ�Yahoo!��Google�ɒ��ڂ���̂��|
1. �T��
| Yahoo! | ||
| ��Аݗ� | 1995�N3�� (�Q�l)���t�[������Ёi�ȉ����t�[�E�W���p���j:1996�N1�� |
1998�N9�� |
| �������J(IPO) | 1996�N4�� (�Q�l)���t-�E�W���p��: 1997�N11�� |
2004�N8�� |
| ��\��(CEO) | �L�������E�o�[�c(Carol Bartz, 1948�N��) (�Q�l)���t-�E�W���p��: ���딎(��\������В�) |
�G���b�N�E�V���~�b�g |
| �]�ƈ��� | 13,500�l�@(2009�N3��������) (�Q�l)���t�[�E�W���p��:�@3,527�l(2009�N3��������) |
20,164�l�@(2009�N3��������) |
| ���ݒn | �{��: 701 First Avenue Sunnyvale, CA 94089, U.S.A. (�Q�l)���t�[�E�W���p��: ��107-6211 �����s�`��ԍ�9-7-1 �~�b�h�^�E���E�^���[ |
�{��: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, U.S.A. (�Q�l)�����I�t�B�X: ��150-8512 �����s�a�J�� ���u�� 26-1 �Z�����A�� �^���[ 6F |
| ���㍂ | 72��850���h���@(2008�N) [7425���~�@��\103/$] (�Q�l) ���t�[�E�W���p��:�@2658���~�@(2008�N�x) |
217��9555���h���@(2008�N) [2��2449���~�@��\103/$] |
| �c�Ɨ��v | 1296���h���@(2008�N) [13���~�@��\103/$] (�Q�l) ���t�[�E�W���p��:�@1346���~�@(2008�N�x) |
66��3197���h���@(2008�N) [6831���~�@��\103/$] |
| ���㍂�c�Ɨ��v�� | 0.2%�@(2008�N) (�Q�l) ���t�[�E�W���p��:�@45.5%�@(2008�N�x) |
30.0��(2008�N) |
| �����v | 4��2430���h���@(2008�N) [437��290���~�@��103/$] (�Q�l) ���t�[�E�W���p��:�@747���~�@(2008�N�x) |
42��2686���h���@(2008�N) [4354���~�@��\103/$] |
| ���� | ���剿�i: 13�h�� ���J���I�l: 33�h��(1996�N4��12��) ��ꗈ���l[�I�l]: 237.50�h��(2000�N1��3��) |
���剿�i: 85�h�� ���J���I�l: 100.01�h��(2004�N8��19��) ��ꗈ���l[�I�l]: 741.79�h��(2007�N11��7��) |
| �������z | �ō��l: ��1280���h��(2000�N1��) [13��8240���~�@��\108/$] (�Q�l) ���t�[�E�W���p�� �ō��l: 5��2400���~(2004�N4��, ���ؑ�ꕔ8�ʂɃ����N�C��) |
�ō��l: ��2190���h��(2007�N11��, �S�đ�5��, IT�ƊE2��) [25��8420���~�@��\118/$] |
2. Yahoo!
�T�v
Yahoo!�́A�W�F���[�E�����ƃf�C�r�b�g�E�t�B���̓�l�ɂ��1995�N�ɐݗ����ꂽ�B���Ƃ���Yahoo!�́A�E�F�u�E�x�[�X�̃R���e���c�������E�m�F�E�ҏW�ł���\�t�g�ł���u�W�F���[��WWW�K�C�h�v����n�܂����BYahoo!�̓��F�́A���O�̃z�[���y�[�W�ɃA�N�Z�X�����l�X�ɗl�X�ȏ������A�|�[�^���T�C�g�Ƃ��ēW�J���ꂽ���Ƃɂ���B
���݂́AYahoo!�̂悤�ȃ|�[�^���T�C�g�𗘗p��������A��������ԗ~���������܂T�C�g��T�������G���W���iGoogle�Ȃǁj�����p����X���������ɂȂ��Ă���B���̌X���̒��AYahoo!���ǂ̂悤�Ɏ��������̃J���[���o���A�����c���Ă�����̂��A���ڂ��W�܂邾�낤�B
���v
| 1990�N | �W�F���[�E�����ƃf�C�r�b�g�E�t�B���A�X�^���t�H�[�h��œd�C�H�w�̗��w�C�m�����擾�B |
| 1993�N | �����ƃt�B���A�E�F�u�T�C�g�̃f�B���N�g���[�̕ҏW���J�n�B |
| 1994�N4�� | �f�B���N�g���[���������Đ����Ƀ��t�[���a���B |
| 1994�N5�� | Netscape�Ђ̃}�[�N�E�A���h���C�Z�������t�[�̃z�X�g���ɂȂ�A����Ђ̃f�t�H���g�E�f�B���N�g���[�ɂ���ƃI�t�@�[�B |
| 1995�N4�� | ��Аݗ��B�x���`���[�E�L���s�^����ЃZ�R�C�A�E�L���s�^�����瓊��100���h������́B |
| 1995�N8�� | �e�B���E�N�[�O�����ō��o�c�ӔC�ҁA�W�F�t�E�}���b�g���ō����s�ӔC�҂Ɣ��\�B |
| 1996�N4��11�� | IPO(�����J)��260�������ꊔ130�h���Ŕ��s�B������Ɋ�����154%�܂Œ��ˏオ�����B |
| 1996�N4��12�� | �����͑O��������i�̔��z�ɋ}���B |
| 1997�N1��14�� | �ŏ��̎l�������Z�\���A���v��9��2000�h���Ɣ��\�B |
| 1997�N4�� | PC���[�^�[�����A���t�[���C���^�[�l�b�g�̃T�[�`�E�A���h�E�f�B���N�g���[�E�K�C�h�̃i���o�[�����ɋ�����B |
| 1997�N5��7�� | �v���p�e�B�ɂ킽��g���t�B�b�N���O���Ƀy�[�W�r���[10�����ɒB�����Ɣ��\�B |
| 1997�N7��29�� | Yahoo!,��ΎO�̊��������\�B |
| 1998�N1��14�� | ��S�l�����A�ꊔ������0.05�h���̗\�z�����v�\�B |
| 1998�N4��8�� | �O��������̃v���r���[��9500����������B |
| 1998�N7��8�� | ��Γ�̊��������\�B |
| 2000�N1��3�� | ����(�I�l)����ꗈ���l237.5�h����t����B |
| 2000�N6��26�� | �����G���W����Google���̗p�i2004�N2��18���܂Łj�B |
| 2008�N1��29�� | �S�]�ƈ���7%�i1000�l�j�̃��X�g���\�B |
| 2008�N11��17�� | �W�F���[������CEO�����C�B��1���A�L�������E�o�[�c��CEO�ɏA�C�B |
| 2009�N7��29�� | Microsoft�Ƃ̋Ɩ���g�\�B |
�ƐсE�V�F�A
�}1 Yahoo!�̋Ɛѐ���
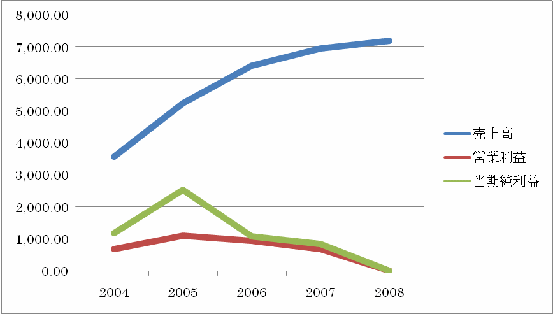
�o��: MSN�}�l�[
�}2 �T�[�`�E�G���W���̃V�F�A(���{�A�A�����J�A���E)
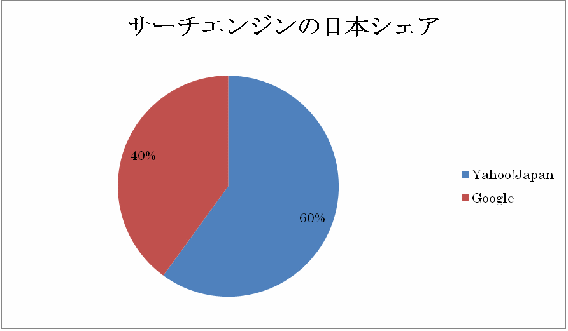
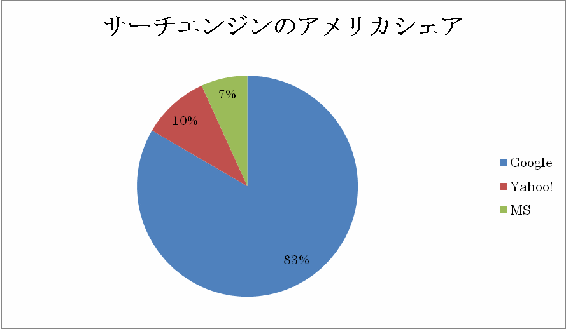
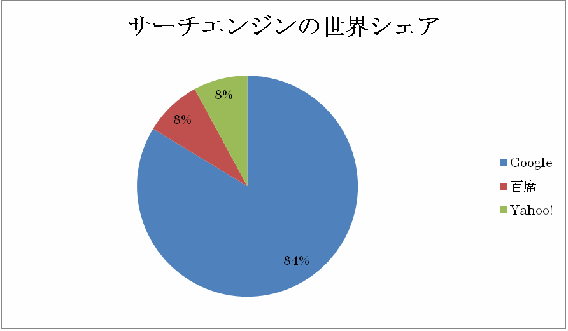
3. Google
�T�v
Google �́A�u���E���̏������A���E���̐l�X���A�N�Z�X�ł��Ďg����悤�ɂ��邱�Ɓv��ڕW�ɁA�����G���W��Google�̑n�ݎ҂ł��郉���[�E�y�C�W�ƃT�[�Q�C�E�u������1998�N�ɐݗ��BGoogle�ɂ��I�����C�������ւ̐V�����A�v���[�`�́A���E���ŏ�����������l�X�̊Ԃɋ}���ɍL�܂����BGoogle��04�N�ɏ��A07�N�ɍō��l(741.79�h��)���L�^���Ă���B���Ȃ݂ɁA���{�@�l��Google�Ђ�01�N�ɐݗ�����Ă���B
���݁AGoogle �́A�ȒP�ȑ���Ő����̈�b�̊ԂɊ֘A���̍����������ʂ������鐢�E�ő�̖��������G���W���Ƃ��čL���]�����Ă���A���̌����V�F�A�͂��܂�A�S���E�̖�7�����߂�܂łɂȂ��Ă���B
Google�̓����́A����グ�̑������L�������ɗ����Ă��邱�Ƃł���B�E�F�u�y�[�W�ɕ\�����ꂽ���Ɛ[���֘A����I�����C���L�����A�\���\�ȒႢ�R�X�g�ōL����̊F�l�ɒ��邱�ƂŎ��v���グ�Ă���BGoogle �̃I�����C���L���́A���[�U�[�ƍL����̗��҂ɂƂ��ĕ֗��ȍL���`�Ԃł���BGoogle �́A���[�U�[�ɑ��ĕ\������郁�b�Z�[�W���L���L���ł��邩�ǂ����m�ɂ���K�v������ƍl���A�������ʂ�A�y�[�W�̃R���e���c�ƍL���Ƃ�K����ʂ��Ă���B�������ʂւ̌f�ڂ�L���Œ��邱�Ƃ͍s���Ă��炸�A�܂��A���p�҂ɂ����K�ړI�Ōf�ڏ��ʂ��グ���肷��Ȃǂ̑���͋����Ă��Ȃ��B
���Ђ̃T�[�r�X�ɂ��ẮA�قƂ�ǐ�`���s���Ă��炸�A���R�~�ōL�܂��Ă������Ƃ������Ƃ��Ă���A����͖{���ɗD�ꂽ���i������A��͌��R�~�ŏ���ɕ]�����L�܂��Ă����B����ɂ���ă}�[�P�e�B���O��p���傫���ߖ�ł���Ƃ����l���ł���B
���v
| 1996�N1�� | �X�^���t�H�[�h��w���m�ے��ɍݐЂ��Ă��������[�E�y�C�W�ƃT�[�Q�C�E�u�����AGoogle�̌��^�ƂȂ�o�b�N�����N�͂��錟���G���W��BackRub�i�o�b�N���u�j���J���B |
| 1998�N9�� | �����[�E�y�C�W�ƃT�[�Q�C�E�u�����AGoogle �Аݗ��B |
| 2000�N6��26�� | Google��Yahoo!�̃T�[�`�G���W���ɍ̗p����A�S���������ʂ̒��J�n�B |
| 2001�N8�� | ���{�@�l�̃O�[�O��������Ђ�ݗ��B |
| 2004�N2��18�� | Yahoo!�̃T�[�`�G���W���̌_��I���B |
| 2004�N4�� | Gmail�T�[�r�X�J�n�B |
| 2004�N7�� | �摜�Ǘ��\�t�g���J�����Ă���Picasa���B |
| 2004�N8��19�� | NASDAQ�Ŋ������J�B�e�B�b�J�[�V���{���́uGOOG�v�B |
| 2004�N10��27�� | �l�H�q����q��B�e�̉摜���f�[�^�x�[�X�������\�t�g��̔����Ă���Keyhole���B���̌�AKeyhole�̋Z�p���g����Google �}�b�v�AGoogle Earth�����J�����B |
| 2005�N5��27�� | Google Print �T�[�r�X�J�n�i�p�ꏑ�БS�������j�B |
| 2005�N12��20�� | AOL�ƒ�g�BAOL�Ɍ����G���W���ƌ����A���^�L����B |
| 2006�N5�� | au (KDDI) �ƒ�g�B�č��ő��SNS�A�}�C�X�y�[�X�ƒ�g�B |
| 2006�N10��9�� | YouTube��16��5000���h���i��1,950���~�j�Ŕ����B |
| 2007�N4��13�� | �L����Ђ́u�_�u���N���b�N�v��31���h���Ŕ����B |
| 2008�N1��24�� | NTT�h�R���ƒ�g�B |
| 2008�N6�� | Yahoo!�Ƃ̃l�b�g�L������ł̒�g�\�B(�Ďi�@���ǂ̌x���Œ�g�����B) |
| 2009�N7�� | NTT�h�R�����AGoogle�g�є���(08�N10���č��ł��AT-���o�C�����甭��)�B |
�Ɛ�
�}3 Google�̋Ɛѐ���(�P��=100���ăh��)
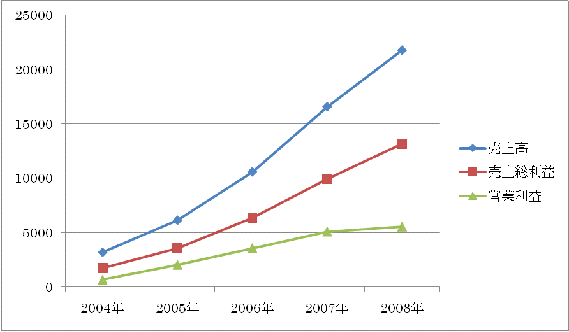
�o��: MSN�}�l�[
Google�́A���t�[�Ƃ̃T�[�`�G���W���_�ꂽ2004�N�Ɋ��������J�A�ȍ~�A�}���ɋƐт�L���Ă���B08�N�̔��㍂��217��9555���h����04�N����31��8922���h���̖�7�{�ɂȂ��Ă���B����́AGoogle�̌����V�F�A��04�N����4���オ08�N����6�����ւƐL�сA����ɂ��L�������������������Ƃ��N���ƂȂ��Ă���ƍl������B���㑍���v���N�X��300���h�����ƁA���肵���y�[�X�ʼnE���オ��ƂȂ��Ă���B2009�N�̑�3�l�����̌��Z�ł́A���㍂��59��4485���h���őO�N������55��4139���h���Ɣ�ז�7���������Ă���B
(�S��: �z�R�ÜA, ���䍂)
IV. �r�W�l�X���f�� �| �L���r�W�l�X�ƃE�F�u�i���ւ̑Ή� �|
1. �L���r�W�l�X
Yahoo!�EGoogle�́A�Ƃ��ɕč��X�^���t�H�[�h��w�̑�w�@���ɂ���ĊJ������A����w�̃T�[�o�[����S���E�ɖ�������邤���ɖ����Ă������BYahoo!�AGoogle�Ƃ��A���傷��ʐM���ׂɑ�w�T�[�o�[���ς����Ȃ��Ȃ�A���O�̃T�[�o�[�ێ��̂��߂ɉ�Љ��̓���H�������A�T�[�r�X�̖����͌p�������B���ЂƂ��A��Б����̂��߂̎��v�����L���ɋ��߁A�L�������̑����ƂƂ��ɐ������Ă������B(2008�N���݂ł��A�S�����ɐ�߂�L��������Yahoo!��88%�AGoogle��97%�ƂȂ��Ă���A�L���ˑ��������Ă���B)
Yahoo!�͑����̃E�F�u�T�C�g���J�e�S���[�ʂɐ�������u�f�B���N�g���^�����v�AGoogle�͓��͂��ꂽ�L�[���[�h�����ƂɌ����G���W���ŊY���E�F�u�y�[�W�𒊏o����u�L�[���[�h�^�����v���T�[�r�X�̎��Ƃ��Ă����B���̌��ʁA�T�C�g�Ɍf�ڂ���L���̃X�^�C�����قȂ��Ă���AYahoo!�̓o�i�[�L���AGoogle�̓L�[���[�h�L��(�����A���^�L��)�𒆐S�Ƃ��Ă����B�����̎嗬���u�f�B���N�g���^�v����u�L�[���[�h�^�v�Ɉڍs���钆�A�L���̎嗬���o�i�[�L������L�[���[�h�L���ւƕς���Ă������B
A. �o�i�[�L����Yahoo!�̐���
Yahoo!�ɂ��v�V�ƃ|�[�^���E�T�C�g�̋���
�C���^�[�l�b�g���o�ꂵ�ĊԂ��Ȃ�1990�N��O���A�z�[���y�[�W���{������ɂ͂��炩���ߓ��Y�y�[�W�̃A�h���X(URL)���擾���������A�u���E�U�[�̃A�h���X����URL�ړ��́i�Ȃ������YURL���u���C�ɓ���t�H���_�v�ɓo�^�j���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������BYahoo!�̑n�Ǝ҃W�F���[�E�����ƃf�C�r�b�h�E�t�B���͑����̃E�F�u�y�[�W���u�r�W�l�X�v�u���W���[�v�Ȃǂ̃J�e�S���[�ʂɐ������A���ׂ����J�e�S���[��H���Ă����ΕK�v�ȃT�C�g�̈ꗗ�ɂ��ǂ蒅����d�g��(�E�F�u�E�f�B���N�g���[)���쐬�����B���킹�āA�f�B���N�g���[�����L�[���[�h�Ō�������f�B���N�g���^�����G���W�����J�������B
Yahoo!�̃f�B���N�g���^�����G���W���́A�l��ō\�z���Ă��邽�߁A���̍����E�F�u�T�C�g�𒊏o�ł���B�܂��A�@�T�v����͂��Ă��邽�ߌ������ʂ̈ꗗ����ړI�̃T�C�g��T���₷���A�A�T�C�g�̃J�e�S������������Ă��邱�Ƃ�����蕪���n��ȂǂɌ��肵���T�C�g��T���₷���A�Ƃ���������������B�������A�T�C�g��l��œ��͂��邽�߁A�����ΏۂƂȂ�T�C�g���𑽂��ł��Ȃ��Ƃ������_������B
�Ƃ�����A�E�F�u�y�[�W�̌����E�{���ɍۂ��AYahoo!�̂悤�ȃE�F�u�E�f�B���N�g�����o�R���邱�Ƃ���ʉ����A���K�҂����������B�����ɁA���̗��K�҂�ΏۂɍL�����f�ڂ��A�L��������A�Ƃ����r�W�l�X���\�ƂȂ����BYahoo!�̓E�F�u�f�B���N�g���⌟���G���W���Ƃ������T�[�r�X���Œ������ŁA�T�C�g�ɍL�����f�ڂ��Ď�����r�W�l�X���f�����m�������B
Yahoo!�ɑ����A���l�̃T�[�r�X����鋣����Ƃ������o�������BYahoo!�A�G�L�T�C�g�A���C�R�X�A�C���t�H�V�[�N�A�A���^�r�X�^��M���ɁA�e�Ђ����ЂƂ̍��ʉ��̂��߁A�V���ȋ@�\��T�[�r�X�i�C�G���[�y�[�W�E�z���C�g�y�[�W���j�������Ď��ЃT�C�g�ɉ�����悤�ɂȂ�B���̋����ɂ́u���[�U�[���T���Ă�����̂�������v�Ƃ������ʃe�[�}���������B�����T�C�g�͑��l�ȃT�[�r�X����鑍���I�ȃT�C�g�ւƈڍs�A���̐V��̃T�C�g�Q��1998�N�ɂ́u�����A���ցv���Ӗ�����u�|�[�^���v�ƌĂ��悤�ɂȂ�A���̃|�[�^���T�C�g�Ԃ�����ȋ����́A�u�|�[�^���푈�v�ƌĂꂽ�B
�����̌����ɂ�蔜��ȃR�X�g���K�v�ɂȂ�A�e�ЂƂ��������B�̕��@�Ƃ���IPO���s���悤�ɂȂ����BIPO�œ��������ɂ���āA�����Ȕ������s����悤�ɂȂ����B���̈�Ⴊ�A1997�N��Yahoo!�ɂ��t�H�[11�����ł���B����ɐ旧��1996�N7���A���t�[�̓E�F�u���[���̗��j���J������ƃz�b�g���[���Ɣ����E��g�̌����������A���s���Ă����B�L�������Ɉˑ�����|�[�^���e�ЂɂƂ��āA���K�҂������ł����ЃT�C�g�ɗ��߂Ă������Ƃ��d�v�ƂȂ�B�E�F�u���[���͍쐬�E�{���ɔ�r�I���Ԃ������邽�߁A���[�U�[���Ɏ��ЃT�C�g�ɑ؍݂�����_�@�ƂȂ�B�܂��A��������E�F�u���[���ɓo�^����A�A�h���X�̕ύX�͖ʓ|�Ȃ��ߑ��̃T�C�g�ւ̃��[�U�[�̈ړ���h�����Ƃɂ��Ȃ�B���̂��߁AYahoo!���͂��߃|�[�^���e�ЂɂƂ��ăE�F�u���[���͔��ɗ~�����T�[�r�X�ƂȂ����B�E�F�u���[���̑��D���������ɂ߂���̂ƂȂ�A�u�|�[�^���푈�v�̖��J���Ƃ��Ȃ����BYahoo!�̓z�b�g���[���̑���Ƀt�H�[11���A�E�F�u���[�����ƂɎQ�������B�E�F�u���[���̑��ɂ��A�`���b�g�E�Q�[���E�V���b�s���O�K�C�h�E�J�����_�[�Ȃǎ��X�ɐV�T�[�r�X������A�C���^�[�l�b�g�̉\���͑傫���L�������B
�o�i�[�L���̓����E�d�g��
Yahoo!���͂��߂Ƃ���|�[�^���T�C�g���f�ڂ����̂́A��Ƀo�i�[�L��(�Ȃ����f�B�X�v���C�L��)�ƌĂ����̂ł������B�o�i�[�L���Ƃ́A�E�F�u�y�[�W��ő��̃E�F�u�T�C�g���Љ����������摜�ł���A�L���Ɏg����摜�i�C���v���b�V�����j�ɂ͍L����̃T�C�g�Ƀ����N������A���[�U�[���N���b�N����W�����v����悤�ɂȂ��Ă���i�N���b�N�X���[�j�B�o�i�[�L���́A�L�����̂��N���b�N���čL����ɂ����ɃR���^�N�g�ł���A�e���r��G���̍L���ƈႢ�N���b�N������L�����ʂ������A�Ƃ��������������Ă���B����ɁA�{���҂��L����̃T�C�g�̏��i���w������A�L����ɂƂ��đ傫�ȗ��v�ƂȂ�B�L���㗝�X���A�u�N���b�N�̉�ۏv�u�N���b�N���Ȃ���Α���͂���Ȃ��v�Ƃ��������蕶��ōL����Ƀo�i�[�L����ϋɓI�ɔ��荞�B
�o�i�[�L���̌��E�E���_
�o�i�[�L���͓��������͗��p�҂ɐl�C�������N���b�N����闦�������������A���N�o�����ɃN���b�N�����������L�����ʂ��������Ă��܂����B���R�͓�������B
��́A�u���̃C���t���[�V�����v���N���A���p�҂̊ԂɃ|�[�^���T�C�g����̓������o�����Ƃ������B�C���^�[�l�b�g�̗��p�҂͔N�X�������Ă�����̂́A�z�[���y�[�W�̐��͂��������y�[�X�Ō����i90�N�㏉���ɂ͐������x���������̂����\���Ƃ������x���ɑ����j���Ă��邽�߁A�z�[���y�[�W��l������̗��p�Ґ��͑��ΓI�Ɍ������Ă��܂��B���ɍs�������z�[���y�[�W���R�̂悤�ɂ���̂ɁA�킴�킴�������Ȃ��L�����N���b�N����l���������Ă������̂����R�ł������B�|�[�^���T�C�g���o���A�����G���W���o�R�Œ��ڃV���b�s���O�T�C�g�ɍs���Ĕ��������郆�[�U�[���������A�|�[�^���T�C�g�̈Ӌ`�͒ቺ�����B�|�[�^���T�C�g�ւ̃A�N�Z�X���������Ă��܂��ƍL���������Ō����邱�ƂɂȂ�B
������̗��R�́A�o�i�[�L�����o���L���傪IT�֘A��ƁE����ҋ��Z�E�A�_���g�Y�ƂȂǏ����Ǝ�Ɍ����Ă������߁A�����悤�Ȋ�Ƃ̍L������\�������悤�ɂȂ�A�O�����Ă��܂������Ƃɂ������B
���̂悤�ȏ̒��Ńo�i�[�L���ɑ���M���x�͒ቺ���Ă������B�����ēo�ꂵ���̂��L�[���[�h�L���������B
B. �L�[���[�h�L����Google�̖��i
�L�[���[�h�L���Ƃ�
�܂��͌����y�[�W���J���A�ۂ̒��̌����G���W���Ɍ������������t����͂���B���̒��Ɏ��������ׂ����L�[���[�h����͂���ƁA�y�[�W�̒��S�Ɏ��������ׂ��L�[���[�h�̌������ʂ��łĂ��邪�A���̉E���ɕ��͂����̍L�����o������B���ꂪ�L�[���[�h�L���ƌĂ�镔���ł���B
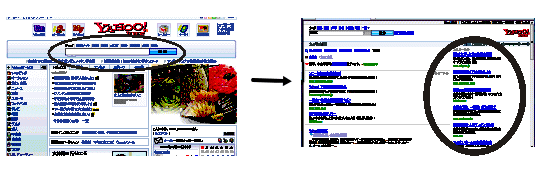
���̂悤�Ȍ����G���W���Ō������ꂽ�L�[���[�h�Ɋ֘A�����L�����������ʂɕ\������V�X�e���������A���^�L���Ƃ������B
�L�[���[�h�L���̋N�� �| �r���E�O���X�̔�����Google�̌����Z�p�v�V
�L�[���[�h�L���̔����҂̓I�[�o�[�`���A�̑n�ݎ҂ł���r���E�O���X�ƌ�����B�O���X��1998�N�ɃJ���t�H���j�A�B�����g���[�ŊJ���ꂽ��c�ł��̃A�C�f�A�\�����B��������c�̏o�Ȏ҂͔F�߂Ȃ������B����ɂ͓�̗��R���������ƍl������B��́A�����G���W���̌������ʂɍL��������A�Ƃ��������Ƃɐl�X���s���Ƃ��Ȃ��������ƁA������́A�L���T�C�Y���������A�o�i�[�̂悤�Ȕh��ȃf�U�C���ɂł��Ȃ����Ƃ����`���ʂ������A�ƍl����ꂽ���ƁA�ł������B
�������A�o�Ȏ҂̌��O�Ƃ͗����ɁA�O���X��1998�N6���ɃL�[���[�h�L�������s�������ʁA�����̃N���b�N����������`���ʂ����邱�Ƃ����������B�O���X�̉�Ђ̌ڋq�͈�N���܂��8��Ђ��A���㑍�z1�疜�h���K�͂ɓ��B�����B�O���X�ɑ�����2002�N�ɃL�[���[�h�L���ɎQ������Google������ȗ��v��������悤�ɂȂ����B�ł́A�Ȃ��L�[���[�h�L���͐l�X�Ɏ����ꂽ�̂��H�Ȃ��o�i�[�L���͖O�����ăN���b�N����Ȃ��Ȃ��Ă����̂ɁA�l�X�͂₷�₷�ƃL�[���[�h�L�����N���b�N����悤�ɂȂ����̂��낤���H
����́AGoogle�ɂ���̋Z�p�v�V�[�@�N���X�^�����O(����)�Z�p�̗̍p�ƇA�y�[�W�����N�E�e�N�m���W�[�̊J���[�ɂ��A�����G���W���̐��\������I�Ɍ��サ�A�C���^�[�l�b�g���p�ɕs���̃c�[���ƂȂ�������ł������B
��L�@�̃N���X�^�����O(����)�Z�p�Ƃ́A���ʂ̈����ȃp�\�R���𐔐��P�ʂŕ��A�����̏W�܂�����̉��z�R���s���[�^�Ƃ��ĉ^�p����Z�p�ł���B������������Ɠ���ւ��������^�R���s���[�^�ƈႢ���݂��e�ՂȂ��߁A�����I�ɑ�������z�[���y�[�W���f�[�^�x�[�X�����邱�Ƃ��\�ƂȂ����B
����A��L�A�̃y�[�W�����N�E�e�N�m���W�[�Ƃ́A�u�l�C�̂���z�[���y�[�W���烊���N�������Ă���y�[�W�͗ǂ��z�[���y�[�W�v�Ƃ�����{���O�ɂ��ƂÂ��z�[���y�[�W�̐M���x�E�d�v�x�������N�t������Z�p�ł���B�����N�����M�p�ł��Ȃ��ꍇ�A�ǂ�ȂɌ����L�[���[�h�𗅗Ă������ɂ�����Ȃ��悤�ɂ���V�X�e���ł��邽�߁A�A���S���Y���E�N���b�J�[(���g�̂Ȃ��z�[���y�[�W�𗐑����������l�דI�Ƀ����N���𐅑������A�����̃z�[���y�[�W�̌����m�����グ�悤�Ƃ���l�X�B�A�_���g�T�C�g�̉^�c�҂Ȃǂɑ�������)�̌��ނɔ��ɗL���������B
��L�@�A�̋Z�p�ɗ��t�����ꂽ�V�������G���W���ɂ���āA�����G���W���ւ̐M�p�x�����A�����͏]���ɔ䂵�Ċi�i�ɉ��K�ɂȂ����B�����������W�łȂ��i�r�Q�[�V����(���ē�)�̎�i�Ƃ��Ďg�p����l���}�����A2003�N���납��C���^�[�l�b�g�̒��S�͌����G���W���ɂȂ�B�u�Ȃɂ�����̂ɂł��܂������v�Ƃ����l���ڗ����đ����Ă������B�����ɁA�����ƘA�������L�[���[�h�L���̎g�p���}�����A�o�i�[�L�������|����悤�ɂȂ�B
�u�o�H�v���̂��̂̉��l
�L�[���[�h�����̏d�v�������̌X���͗l�X�ȓ��v�ɂ���Ď�����Ă���B���Ƃ��A�l�b�g���C�e�B���O�X�Ђ�2005�N11���C���^�[�l�b�g��ɂ��������s���Ɋւ���ӎ��������ʂ\�B�I�����C���V���b�s���O�Ȃǂł̏���s���͌����G���W�����d�v�ȋN�_�ƂȂ��Ă���i��ʓI�ȏ��i�w���F50���@���s���i�̍w���F86���@�d�q�@��F74���j���Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B
�O���X�́A�l�X�̍w���s�����A�L�[���[�h�����̌��ʂ���N���邱�Ƃɒ��ڂ��A�u���\���ǂ������G���W���ł���A���̌������ʂɊ�Ƃ̓J�l���������낤�B�C���^�[�l�b�g�������w�o�H�x�������d�v�ł���v�ƑM�����B���Ȃ킿�A����L�[���[�h�ɑ��錟�����ʂ�\�������y�[�W�Ɋ�ƍL���̃X�y�[�X��݂��A���̃X�y�[�X�̎g�p����̔����邱�Ƃ��v�������̂ł���B���̌��ʁA�l�X�ȃL�[���[�h�Ɋ֘A�������l�Ȍ������ʂ��L���������Ɖ������B���̂悤�ȃL�[���[�h�L���ɂ��o�ς̔�剻�́u�T�[�`�G�R�m�~�[�v�Ƃ��Ă��悤�ɂȂ�B
�L�[���[�h�L��(��: Google �A�h���[�Y)�̂�����
Google Adwords��p���ăL�[���[�h�L�����o�����߂̎菇�͉��L�̒ʂ�ł���B
�I�[�N�V��������: ���z����D���A�L�[���[�h�Ɉ�ԍ����l�i�������l�����D����d�g�݁B�L�������́u�N���b�N�P���v�ɂ���Č���B��Ƃ�1�N���b�N���Ƃɒ�߂��f�ڗ����x�����B
��j�u��w�v�̃L�[���[�h�ŃI�[�N�V�������������ʂ����L�̏ꍇ
�@�P�E�哌������w�@200�~
�@�Q�E�吼��w�@�@�@100�~
�@�R�E�k���w�@�@�@150�~
�f�ڏ��͂P�E�R�E�Q�̏��ƂȂ�B�����̓X�܂��������ꍇ�g�b�v�y�[�W�Ɏ��܂炸2�y�[�W�ڂֈڍs���邱�ƂɂȂ�B��Ƃ̓g�b�v�y�[�W�Ɏ����̍L��������悤���D�z��ނ�グ�Ă����B
�L�[���[�h�L���̗��_
�O�[�O���A�h���[�Y�̂悤�ȃL�[���[�h�L�����g�p���邱�Ƃ́A�L����E����҂Ƃ��Ƀ����b�g���������B
�܂��A�L���呤����݂�ƁA�L�����u���O��z�[���y�[�W�̓��e�ɂƂ��Ȃ��Č����̂ŁA�L�������Ă������҂ɂƂ��ĕs���R�ɍL����ł���Ă���A�Ƃ�����ۂ����Ȃ��B����āA�N���b�N���������A�L����ɂƂ��Ă������̃z�[���y�[�W�ւ̃A�N�Z�X�A�b�v�ɂȂ���B�܂��A�o�i�[�L���ɔ�ׁA�L��������r�I�����ł��ށB�o�i�[�L���́A������x�X�y�[�X���Ƃ�̂ŁA���̂Ԃ��������邪�A�L�[���[�h�L���Ȃ�X�y�[�X���ŏ��ł���̂ŁA���܂肨����������Ȃ�����ł���B���̌��ʁA�����L������������҂ɔF�m���Ă��炦�Ȃ�����������Ƃ��L�[���[�h�L�����o����悤�ɂȂ�A�S���E�S���E�K�͂Ŕ����L����悤�ɂȂ����̂ł���B
����A����ґ�����݂�ƁA�w�肷��L�[���[�h�ɑ��錟�����ʂ�L�[���[�h�Ɋ֘A����y�[�W�ɂ̂ݍL�����\�������̂ŁA�K�v�ȏ�X���[�Y�ɓ�����B
�L�[���[�h�L���̖��_
�O�q�̂悤�ɁA�O�[�O���A�h���[�Y���ˋ����錟���G���W���́A�z�[���y�[�W�̐M���x�Ɋւ��郉���L���O�Ɋ�Â��Č������ʂ���邪�A���̃z�[���y�[�W�̃����L���O����O�̕]���ɍ��E���ꂷ�������ӌ������f����ɂ����A�Ƃ������_���w�E����Ă���B����ɁA�������ʂɂ����鎩���̃z�[���y�[�W�̕\�����ʂ��Ӑ}�I�ɏグ�悤�Ƃ��鋣�������������Ă���B
�܂��A�A�h���[�Y�̃V�X�e���́A�L���\�����_�ł͂Ȃ��N���b�N�̎��_�ʼnۋ����������A�������ꂽ�P���y�[�W�ɑ��݂����v�ȒP��ɍ��킹�Ċ֘A�L�����\�������ƂȂ��Ă��邪�A�y�[�W�Ɉ�x���o�ꂵ�Ȃ��P����L�[���[�h�Ƃ��Đݒ肵�Ă��A�������֘A�����������f���ĕ\�����Ă��܂����Ƃ�����B����ɁA�p�ꂩ����{��ւ̑Ή��͂̎コ���w�E����Ă���B
2. �E�F�u�i���ւ̑Ή��@-Web1.0�IYahoo!�AWeb2.0�IGoogle-
Yahoo!��Google�̓N�w�̈Ⴂ
Yahoo!�́A�d���������Łu�l�Ԃ̉�݁v���d�v�ƍl���A�l�Ԃ���邱�ƂŃ��[�U�[�����x���オ��ƐM����̈�ł͐ϋɓI�ɐl�Ԃ���݂�����B���Ƃ��j���[�X�ҏW�ɂ͗D�G�Ȑl�Ԃ̎��_���K�v�ƍl���AYahoo!�g�s�b�N�X�Ɍf�ڂ���j���[�X�̑I����l�ԂɈς˂Ă���B����AGoogle�́A�d���������ŋɗ́u�l�Ԃ̉�݁v�͔�����ׂ����A�Ƃ����l���������B���Ƃ��AGoogle News�̕ҏW��Google���J�������A���S���Y���ɂ���Ď�����������Ă���B
Web���_����݂�Yahoo!��Google�̈Ⴂ
Yahoo!�͐���ґ��������I�ɃR���e���c����Ă���A�Ƃ����_��Web1.0�I�Ƃ�����B���̃T�C�g�͐V���E�G���E���W�I�ETV�Ɏ�����܃��f�B�A�Ƃ�������B����AGoogle�́AGoogle Map�Ɋ�Â����T�C�g�̊J�݂�F�߂�ȂǁA���[�U�[�ƂƂ��ɃR���e���c��n�����Ă���(���[�U�[�Q���^)�A�Ƃ����_��Web2.0�I�Ƃ�����B���ہA���[�U�[�̎Q���������Ȃ�Ȃ�قǁA�f�[�^�����~�ς���A�W���m�Ƃ��Ẵ��f�B�A(UGM: User Generated Media)�̉��l�����܂�B�܂��A���[�U�[�������I�ɑn��o�����R���e���c�������o�[�ŋ��L����A�\�[�V�������f�B�A(SM: Social Media)�Ƃ��Ă̐��i�����悤�ɂȂ�BGoogle��UGM�ESM�ւ̓]���Ɏh������AYahoo!�����̓�ւ̓]�������s���ׂ��\�z������Ă���B
Web1.0��Web2.0�̈Ⴂ
| Web1.0 | Web2.0 | |
| ��M | ���ҁi���Ɓj����̈���I�ȏ�M�E�� | ���[�U�[�i��ʐl�j�̉���ɂ��V���ȃT�[�r�X |
| �o�c���O | ����؎�̂̌o�c �i������20���̏��i��80%�̗��v�j |
�z�[���y�[�W�ł̏��i�A�N�Z�X�����E�]�� �i���㉺��80%�̏��i������؏��i�j �������O�e�[���r�W�l�X |
| �T�[�r�X | HTML�ACGI �i���R�ȏ�������������j |
JAX�A�_�C�i�~�b�NHTML �i���[�U�[�����R�ɐ����E�z�u�j |
HTML�FWeb�y�[�W���L�q���邽�߂̃}�[�N�A�b�v����BW3C���쐬���Ă���K�i�ŁA�ŐV�ł́AHTML�S�C�O1�BHTML�͕����̘_���\���〈�h���Ȃǂ��L�q���邽�߂Ɏg�p�����B�܂��A�����̒��ɉ摜�≹���A����A���̕����ւ̃n�C�p�[�����N�Ȃǂߍ��ނ��Ƃ��ł���B
CGI�FWeb�T�[�o�[���AWeb�u���E�U����̗v���ɉ����āA�v���O�������N�����邽�߂̎d�g�݁B�]���AWeb�T�[�o�[�͒~�ς��Ă��镶�����������o���邾���ł��������ACGI���g�����Ƃɂ���āA�v���O�����̏������ʂɊ�Â��ē��I�ɕ������쐬���A���o���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
JAX�FSun�@Microsystems�Ђ�Java�̊g���@�\�Ƃ��Ē��Ă���BXML�f�[�^�����p��API�Q�BXML�p�[�T�[�@�\������JAXP�iJava API for XML Processing�j�ASOAP�f�[�^����M���s��JAXM�iJava API for XML Messaging�j�̂Q��ނ������[�X����Ă���B
�_�C�i�~�b�NHTML�FWeb�y�[�W�ɗe�ՂɑΘb�����������邱�Ƃ��ł���HTML�̊g���d�l�BHTML�����̒���JavaScript��VBScript�ŃX�N���v�g�ߍ��ނ��Ƃɂ��A�v���O�C����ActiveX�R���g���[���AJava�A�v���b�g�Ȃǂ́A�e�ʂ��傫���������d���Z�p���g�����ƂȂ��A���������đΘb����������Web�y�[�W���쐬���邱�Ƃ��ł���B
Web2.0�̒�`
Web2.0�Ƃ́A�Q�O�O�O�N�㒆���ȍ~�ɂ�����A�E�F�u�̐V�������p�@���w���B���̌��t���ŏ��ɗp�����͕̂ďo�ŎЃI���C���[�E���f�B�A��CEO�̃e�B���E�I���C���[�ł���BWeb2.0�̓����Ƃ��Ĉȉ��̂V�_���g������B
�����O�e�[��: �]���̏����r�W�l�X�ł́A����̏��20%�̏��i�Ŏ��v�S�̂�80%��グ��u80�F20�̖@���v�ɏ]���Ă����B����ɑ��A���܂蔄��Ă��Ȃ�80%�̏��i�Ńj�b�`�Ȏ��v�ɉ����A�r�W�l�X�𐬂藧�����邱�Ƃ������O�e�[���r�W�l�X�Ƃ������B
�e�B���E�I���C���[�ɂ��ƁA���̂V���������������Ă�������A����̕���œˏo���Ă�������Aweb2.0�I���Ǝw�E���Ă���B
���̂V�v�f�̂Ȃ��ōł������I�Ȃ̂́A�Q�`�S�ɋ��ʂ���L�[���[�h�u���[�U�[�Q���^�v�ł���B���Ȃ킿�v���b�g�t�H�[���Ƃ��Ă�web�����p�����ŁA����ґ��������I�ɃR���e���c�����̂ł͂Ȃ��A���[�U�[�ƈꏏ�ɃR���e���c��n������Ƃ����_�ł���B�����͏��̑����Ǝ肪�Œ肳�ꑗ���ւ̈���I�ȗ���ł�������Ԃ��A�����Ǝ肪���������N�ł�web��ʂ��ď��M�ł���悤�ɕω��������ł���B
�����āA���[�U�[�̎Q���������Ȃ�Ȃ�قǁA�f�[�^�[����葽���~�ς���A���ʁA�W���m�Ƃ��Ẳ��l�����܂�B�����ʂ̌��t�ŕ\������ƁA���[�U�[�E�W�F�l���C�h�E���f�B�A�iUGM�j�ƂȂ�B�����āA���[�U�[�������I�ɑn��o�����R���e���c�������o�[�ŋ��L���邱�Ƃ���A�\�[�V�����E���f�B�A�ł���Ƃ�������B
Web2.0�̑�\��
Web2.0�̑�\�I�ȗ�Ƃ��ẮA�uWikipedia�v�E���{�b�g�^�����G���W���ESNS�E����f���E�u���O�Ȃǂ��g������B�����̏���҂�������E���̔��M���ɂȂ������̂́A���ׂċ��`��Web2.0�̒�`���݂����B
��̓I�ȋZ�p�m�Ɏ����p��ł͂Ȃ��}�[�P�e�B���O�E�l�b�g�T�[�r�X�ƊE�ň�l�������Č���邽�߁A�u�o�Y���[�h�v�Ƃ�������B����䂦�P�Ȃ��`����Ƃ��Ďg�p����鎖�������A���ɂ���@��͑����Ƃ��A���̎��Ԃ̗����͓��{�ł͐Z�����Ȃ������B
�����ʂ̗������ƁA��L2�́u���[�U�[�Q���^�v�Ƃ��ẮAGoogle�����Ă���Google Maps��AAmazon.com�̃J�X�^�}�[���r���[�AGoogle�̃y�[�W�����N�̎d�g�݂Ȃǂ������邱�Ƃ��ł���B��L5�́u�����O�e�[���v�̗�Ƃ��ẮAAmazon.com��Google AdSense�Ȃǂ������邱�Ƃ��ł���B
UGM�̂��߂̊�Ս\�z
�����̃E�F�u�y�[�W���Ȃ��A�u�C���^�[�l�b�g���E�̏W���m�v����邽�߁AGoogle�͖c��ȃf�[�^�E�C���t���𐢊E�S��ɂ킽���ĕۗL���Ă���BGoogle�́A�E�F�u���N���[���E�����E�������A���E���̐l�X���L�[��ł�����Gmail�EGoogle Apps�EBlogger�EGoogle Reader�������������A����ɂ̓O�[�O���v���b�N�X�i�{�Ёj�����z���関���v���W�F�N�g���S���������Ă���B�Ƃ�ł��Ȃ��R���s���[�^�����\�͂��v�������̂͑z���ɓ�Ȃ��B
���̃f�[�^����������T�[�o�[���u���Ă���f�[�^�Z���^�[��2008�N�i�K�Ōv36�����B�|�����č�����19�����A���[���b�p12�����A�A�W�A3�����A���V�A�Ɠ�Ă��e1�����B�������ݗ\��n�ɂ͑�p�A�}���[�V�A�A���g�A�j�A�ƁA���Ƃ̓O�[�O����466�G�[�J�[�̓y�n���w�������ƕ�ꂽ�ăT�E�X�J�����C�i�B�u���C�Y�E�b�h�������Ă���\��������B
Google�͏��L���Ă���T�[�o�[�̐��m�ȑ䐔�����\���Ă��Ȃ����A�e�f�[�^�Z���^�[�ɂ͗D�ɐ��\����̃T�[�o�[������Ɛ��������BGoogle�t�F���[�ł���W�F�t�E�f�B�[�������킭�A�e���b�N�ɂ�40��̃T�[�o�[�����[����Ă���A���̃��b�N���琔���P�ʂ̃N���X�^�[���`���A���̃N���X�^�[�𐢊E���ɐݒu���Ă���B
�܂��f�B�[�����́u�M�����̍����n�[�h�E�F�A��1�䎝�����A�M�����͂��قǍ����Ȃ��n�[�h�E�F�A��2�䎝�������������Ƃ����̂��AGoogle�̍l�����B���̏ꍇ�A�M�������\�t�g�E�F�A���x���Œ���K�v������B1����̃}�V�����ғ����Ă���A�����A�������̏Ⴗ�邾�낤�v�Ƃ��q�ׂĂ���B
�E�F�u����̂��߂�OS�J��
Google�͊�ƂƂ̋����J���ɂ��Ǝ��̐V����OS�uGoogle Chrome�v�����삵�Ă�����B����́A�I�[�v���\�[�X�^�̃l�b�g�u�b�N�����̃v���b�g�t�H�[���ɂ��Ă������̂ł���B�O�[�O�������n�Ǝ҂̃����[�E�y�C�W���́A�u�قƂ�ǂ̂��Ƃ��u���E�U�[���łł��鎞��ɂ́A�]����菬�����ĒP����OS���K���Ă���v�ƌ��A�E�F�u����ɍœK�����ꂽOS�̕K�v�������������B
�܂��A�ŋ�Google�́A�����J�����s���Ă����Ɩ������߂Č��\�����BAcer�AAdobe�AASUS�AFreescale�AHewlett-Packard�ALenovo�AQualcomm�ATexas Instruments��8�Ђ����A�����ȊO�ɂ������̊�ƂƋ����J�����s���Ă���A�u�f���炵�����[�U�[�̌��������炷�[����v�E��������v�Ƃ��Ă���B������܂��Aweb2.0�I�ȓ����ł���B
(�S��: �c������, ���c�m��, ���q�T��, ��㏫)
1. �T��
| ���t�[�E�W���p�� | ||
| ���ԑ������� (2009�N1�� comScore Japan����) |
35���� | 26���� |
| �����V�F�A(���������x�[�X 2009�N1�� comScoreJapan����) (�Q�l: �č� 2009�N3�� ���E 2009�N6�� comScore����) |
51.3% Yahoo! 20.5% Yahoo! 6.5% |
38.2% Google 63.7% Google 68.9% |
| ���p�p�x1�ʂ̌����T�C�g (2005�N11�� �A�E���R���T���e�B���O����) |
57% | 34% |
| �g�b�v�y�[�W�ݒ� (2007�N3�� ���o���T�[�`����) |
61% | 9% |
| ���ԑ����p���� (2007�N6�� Net Ratings����) |
80.6���� | 29.2���� |
| �o�c�`�� | ���n�� (���t�[�E�W���p���� �Ǝ��H�����т�) |
�O���[�o���o�c (���{�@�l�� �O���[�o���`�[���̈��) |
| ���p���� | �ꕔ�ۋ��� | ���� |
1998�N�̑n�Ƃ����10�N�AGoogle�͔���E���v�E�������z�Ƃ��ɐ��E�ő�̃C���^�[�l�b�g��Ƃɐ��������B���߂̌����G���W���Ƃ��ẴV�F�A(���ԑ��������x�[�X, comScore�В���)�͕č�����63.7%(2009�N3��), �S���E��68.9%��1�ʂ�Ƒ����Ă���B
�������A���{�����ɖڂ�������Ɨl���͑S���قȂ��Ă���B�����V�F�A(���ԑ��������x�[�X, comSocore����)�Ŏ�ʂ��߂�̂̓��t�[�E�W���p��(51.3%)�ł���AGoogle��2��(38.2%)�ɂƂǂ܂��Ă���B���t�[�D�ʂ̍\���́A���̎w�W�i���p�p�x�E�g�b�v�y�[�W�ւ̐ݒ�E���ԑ����p���ԂȂǁj�Ɋ�Â������ł����l�Ɋώ@�ł���B���E�ł�Google��Yahoo!�����|���Ă���ɂ�������炸�A���{�ł̓��t�[�E�W���p����Google���������ċ�����ۂ��Ă���̂͂Ȃ��Ȃ̂��낤���H
�����̈�[�̓��t�[�E�W���p����Google���{�@�l�̌o�c�`��(�č��{�ЂƂ̊W)�ɈႢ�ɂ���B���t�[�E�W���p����1996�N�̐ݗ��ȗ��A�č���Yahoo!�{�Ђ���͓Ɨ������o�c���s���Ă����BYahoo!�T�C�g�̃f�U�C���E���e����{�ɍ��킹�Ē�������ƂƂ��ɁA�I�[�N�V����(���t�[�E�I�[�N�V����)�AADSL(Yahoo!BB)�ȂLjꕔ���Ƃʼnۋ��������A���v�x�[�X�̊m�ۂɐ��������B�Ǝ��̎��v���������ƂŁA�o�c�̎��含��ۂ��Ă����Ƃ�������B����AGoogle���{�@�l��2001�N�̊J���ȗ��A��ɃO���[�o���`�[���̈�Ƃ��Ă̌o�c���s���Ă���B�Ј��������J�������Ă���l�Ȃ猟���`�[���A���o�C���S���̐l�Ȃ���o�C���`�[���Ƃ������`�ŃO���[�o���ȃ`�[��������ē����Ă���B�������͂��ߊe��T�[�r�X�̒Ɋւ��ẮA�č��{�ЂƓ��l�A��������������Ă���B
2. Yahoo! (���t�[�E�W���p��)
A. ���{�ł̎��ƓW�J
| 1996�N | ���t�[�E�W���p���ݗ��B |
| 1997�N | �X�|�[�c���A�����A��Ə��̒J�n�B |
| 1998�N | My Yahoo�A���t�[�f���A���t�[�Q�[���A�n�}���̒B |
| 1999�N | ���t�[�I�[�N�V�����A�V���b�s���O�A�O�����T�[�r�X�J�n�B |
| 2000�N | ���t�[���o�C���i�����A�V�C�A�I�[�N�V�����j���o��A�I�[�N�V�����L�����B |
| 2001�N | ���t�[��ADSL���ƁAYahoo! BB�̊J�n�\�B |
| 2002�N | Yahoo!��z���X�^�[�g�AYahoo!�t�@�C�i���X�Ɋm��\�����Z���^�[�ݒu�B |
| 2003�N | Yahoo!�j���[�X���L���R���e���c�u�V���L�����f�����v�����J�B |
| 2004�N | Yahoo!�m�b�܌��J�AYahoo!���H��ʏ��A�u�ЊQ���\���@�\�v��lj��B |
| 2005�N | Yahoo!�|��AYahoo!�ی��AYahoo!�u���O�A���o�C����Yahoo!�n�}�����J�J�n�B |
| 2006�N | �\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X�iSNS�j���X�^�[�g�B |
| 2007�N | ������ЃC���^�[�X�R�[�v�����t�[������Ђ̎q��Љ��B |
| 2008�N | Yahoo!���o�C����Yahoo!�w�b�h���C���j���[�X���o��B |
B. ���t�[�W���p�������̗��R
���t�[�W���p���̐����̗��R�Ƃ��đ��ɋ�������̂́A�����ł̓��{�i�o�ł���B���t�[�W���p���͕č���Yahoo!�Ɠ��{�̃\�t�g�o���N�Ƃ̍��ى�ЂƂ���1996�N�ɐݗ����ꂽ�B���̎��A���{�������t�[�E�W���p���̑��������̂U�����擾�������ƂŁA���t�[�E�W���p���̉^�c�͓��{�l�Ɉς˂��邱�ƂƂȂ����B����A�O�[�O�������{�@�l��ݗ������̂�2001�N�ƒx����Ƃ����B���{�l�́A�V�������\���ǂ����̂��o�Ă��Ă����ݎg���Ă�����̂��g�p��������Ƃ��������������Ă���B���̂��߁A�O�[�O���������{�i�o���Ɏ��s�������t�[�E�W���p���͈�ʗ��p�҂̈͂����݂ɐ��������B
���t�[�E�W���p���̐����̑��̗��R�Ƃ��ẮA�I�[�N�V�����Ȃǂ̃T�[�r�X�ɑ���ۋ����̓�������������B���t�[�E�I�[�N�V������99�N�ɊJ�n���ꂽ�B�����͖����Œ��Ă�����2001�N�ɖ{�l�m�F�A�g���u���h�~�Ȃǂ̗��R�ɂ��A�����Q�X�S�~�̗L�����ƂȂ����B�L�����ƂȂ��������͈ꎞ�I�ɏo�i���������������A����ɏo�i�������ɖ߂肾�����B�����Č��݂ł́A�����Q�X�S�~���x�����v���~�A�����[�U�[���U�P�T���l�ɂ܂ő��������B�L��������́A�N�X�����̈�r�����ǂ��Ă���(���}�Q�ƁB)
�}�@���t�[�E�W���p���̗��p�҂̐���
�i2004�N3������2006�N3��, �P�ʁ����l�j
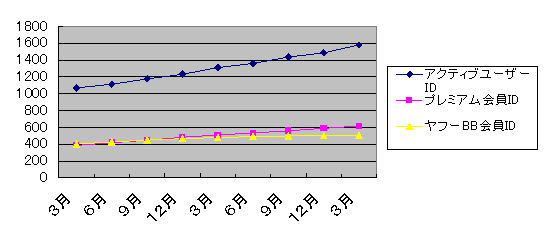
C. ����̉ۑ�
���t�[�E�W���p���̍���̉ۑ�Ƃ��ẮA�傫�������ć@�R���V���[�}�[�̐������Ԃւ̐i�o�A�A�����N�w�E�P�O�テ�[�U�[�̊l���A�B�l���̕ی��3�_����������B
���̉ۑ�i�@�R���V���[�}�[�̐������Ԃւ̐i�o�j�̒B���̂��߂ɂ́A�Ɠd���[�J�[�Ƃ̒�g�ƃ��t�[�E�W���p���̃��o�C�������傫�Ȗ��������B�Ɠd���[�J�[�Ƃ̒�g�Ɋւ��ẮA���t�[�E�W���p���́gEverywhere��́h�Ƃ��āA�Q�[���@�E�J�[�i�r�E�e���r�Ȃǂ̃��j�^�[��������t�[�̃T�[�r�X���͂����Ă���B���̃T�[�r�X���������邽�߂ɂ́A���{���[�J�[�Ƃ̘A�g���s���ƂȂ�B�������t�[�̓e���r�Ƃ̘A�g�ɂ����āA�V���[�v�Ⓦ�ŁA�\�j�[�ȂǂƘA�g���Ƃ��Ă���B�������A���t�[�E�W���p���Ƃ̘A�g�́A���{�����݂̂̓W�J�ɗ��܂��Ă��܂��\�����傫���B���̂��ߐ��E�K�͂ł̓W�J����]���Ă��郁�[�J�[�ɂƂ��ẮA�O�[�O���̕������ǂ��A�g����ɂȂ�B���o�C�����Ɋւ��Ă����t�[�E�W���p���͑O�����ȓ����������Ă���B���t�[�̓p�\�R���p�R���e���c�����X�ɁA�g�єŃ��t�[�ֈڐA���Ă���B���݂ł͖�T�O�̃T�[�r�X���ڐA����A���t�[�E�I�[�N�V���������o�C���Ή����T�[�r�X�����ꂽ�B���t�[�̃��o�C���g��͒��X�Ɛi�݁A�F�m�x���X�R���ƂȂ����B
���̉ۑ�i�A�����N�w�E�P�O�テ�[�U�[�̊l���j�̔w�i�Ƃ��ẮA���t�[�T�C�g�̗��p�҂̔N��w�̂����A�T�T�Έȏオ�T���A�P�V�Έȉ����U���Ə��Ȃ����Ƃ���������B����́A���ɒc��̃C���^�[�l�b�g�̗����オ�邱�Ƃ��\�z�����B���̂��ߒc����ǂ̂悤�Ɏ�荞��ł��������A�l�b�g�r�W�l�X�ɑ傫�ȉe����^���邾�낤�B
��O�̉ۑ�i�B�l���̕ی�j�̒B���̂��߂ɂ́A���ǂ��T�[�r�X��������ŁA���p�҂����S���ė��p�ł���l�b�g���𐮂���K�v������B��̓I�Ƀ��t�[�́A�l���ی�ɂ�����g�l���擾���̓��Ӂh�ȂǂW�̍s���w�j�������Ď��g��ł���B
3. Google (�O�[�O�����{�@�l)
A. ���{�ł̎��ƓW�J
�T��
| 2000�N | 9�� | Google����{�ꌟ���ɑΉ��\���B |
| 12�� | NEC�u�r�b�O���[�u�v�����T�C�g�Ɍ����T�[�r�X��B���{�����ł�Google�����G���W����ꍆ�ƂȂ�B�]���ɂȂ������E�����x�̌����A���{��y�[�W���茟���A�r�b�O���[�u�y�[�W���茟���Ȃǂ�����Ƃ���B | |
| 2001�N | 2�� | �n�Ǝ҃����[�y�[�W�ADEMO2001(IT�x���`���[��Ƃ̋Z�p�W����)�̂��ߏ������B�u����Google�̍��@�\���i��13����web�y�[�W�̍������A�������7000�����̌����v���ɑς���拭���A����0.9�b�Ō������ʂ�\������X�s�[�h���A�o�i�[�L����4�{�̃N���b�N�����������A���^�L���j���A�s�[������ƂƂ��ɂ�i���[�h�g�тւ̑Ή��\�B |
| 3�� | Google�Џ��̊C�O�I�t�B�X���I�[�v������́u�Z�����A���^���[�v�i�����j�ɊJ�݁B | |
| 2005�N | 6�� | Google Earth���J�B |
| 2006�N | 7�� | EZweb��Google�����G���W���̗p�B |
| 9�� | Google Earth�n�}�@�\�lj��B | |
| 10�� | You Tube�����B | |
| 2007�N | 7�� | KDDI�ƒ�g���AGmail�@�\����荞�E�F�u���[��(au one���[��)��B�E�F�u���[����KDDI�g�b�v�T�C�g�ɔz�u�A��e�ʂ̃f�[�^�ۑ��E�ߋ����[�������Ȃǂ��\�Ƃ����B |
| 2008�N | 1�� | NTT�h�R���ƒ�g���A�����T�[�r�X�E�����A���L���A�A�v���P�[�V������B |
| 2009�N | 7�� | NTT�h�R���ƒ�g���A�O�[�O���g�т�̔��B�O�[�O���g�т̓A�b�v���Ђ�iPhone�Ɠ��l�̃X�}�[�g�t�H��(�d�b�EPDA��̂̍��@�\�g�ѓd�b)�ŁA�t���^�b�`�p�l�����̗p�AGmail�E�X�g���[�g�����[���͂���Google�Ђ̒���e��T�[�r�X���X���[�Y�Ɏg�p�\�B�܂��AOS��Google���J������Android���g�p���AAndroid�}�[�P�b�g����A�v���P�[�V�������_�E�����[�h�ł���B |
Android�}�[�P�b�g:�@Apple Store�ɑR����Google���J�������A�J���҂����R�ɃA�v����o�^�E�̔��ł��A���E���̃A�v����L���ōw���ł����̂��ƁB���̎��v�̂V�����J���ҁA�R����Google���擾���邵���݂ɂȂ��Ă���B�j
i���[�h�Ή��𒆐S�Ƃ������{�s��Ή�
���{��i���[�h�́A�a������1999�N���_�ł́A�g�ѓd�b�����Web�A�N�Z�X�̍Ő�[��i�Ƃ��āA���E�I�ɂ����ڂ��W�߂Ă����B�O�[�O���n�Ǝ҂̃����[�E�y�C�W���A���̐�i���ɋ����������A2001�N�Ƃ��������̒i�K����Google������i���[�h�ɑΉ��i�����Ō������y�[�W���g�їp�Ɏ����I�ɐ��`�j�����Ă����B���N�A�O�[�O�����̊C�O�I�t�B�X����{�ɊJ�݂���������A���{�̌g�ѓd�b�s��ւ̊��҂�������������Ƃ�����B
���̌���A�O�[�O�����{�@�l�𒆐S��i���[�h�Ή��̏[������i�߂Ă���BGmail��O�[�O���J�����_�[�Ƃ������قƂ�ǂ̃T�[�r�X���ŐV���g�ѓd�b�Ŏg����悤�ɂ����ق��A�ꕔ�@��ɂ�GPS�Ή��̍��@�\�O�[�O���}�b�v�E�A�v���P�[�V�������p�ӂ����B2006�N��YouTube������́AYouTube����{�̌g�ѓd�b�̑����̋@��ɑΉ������Ă���B
���̑��AGoogle�ɘH�������T�[�r�X������������A�n�}�T�[�r�X(Google Map)���w�𒆐S�Ƃ��������ɒ�������ȂǁA���{�Ȃ�ł͂̓��ꎖ��ɍ��킹���T�[�r�X���s���Ă���B
�m���x����̂��߂̓w��
�O�[�O���́A���{�i�o�̎����Ɋւ��ă��t�[�E�W���p���ɒx����Ƃ�A���p�x�Łu���t�[�E�W���p���Ɏ���2�ʁv�Ƃ������甲�����ꂸ�ɂ���B���Ƃ����Ă�葽���̓��{�l�ɃO�[�O����m���Ă��炤���߁A�ȉ��̂悤�ȃ}�[�P�e�B���O�E�L���ɂ��͂���ꂫ���B
���p�Ҋg��̂��߂̓w��
���t�[�W���p���قǑ̌n������Ă��Ȃ����A�O�[�O�����l�X���p�\�R�����痣��Ă��鐶�����Ԃɐi�o���悤�ƈȉ��̂悤�Ȏ��݂��s���Ă���B
B. ���{�ł̐L�єY�݂̗��R
C. ����̉ۑ�
(�S���F ��������, �ɓ��G��)
V�h. Microsoft�EYahoo!��g�Ƃ��̔w�i
�P. Microsoft�EYahoo!��g�̔w�i
2009�N7��29���AMicrosoft��Yahoo!�̓C���^�[�l�b�g�����E�L�����Ƃł̒�g�\�����B2008�N1����Microsoft��Yahoo!�ɔ�����Ă��o�����ۂ́AYahoo!�̑n�Ǝ҂ł���CEO(����)�ł��������W�F���[�E�������𒆐S��Yahoo!���o�c�w�����ۂ����o�܂����������A���N����ɒ�g�ɓ]���邱�ƂɂȂ����B���̔w�i�ɂ́AGoogle�̍U���ɑR���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�Yahoo!�AMicrosoft���ꂼ��̋ꂵ������������B
1990�N��㔼�`2000�N�㏉���A�|�[�^���T�C�g�̑S�����ɂ́AYahoo!�̓��[�U�[�̎x���āA�T�C�g�ʉ{���Ґ��Ŏ�ʂ��ւ��Ă����B�������A�����A���^�L���̊J����Google�̌��ɉ��A����E���v�ʂł�Google�Ƃ̊i�����L�����Ă������B
���}1��Yahoo!, Google��2004�N�`2008�N�̔�������������̂ł���BYahoo!�̔����2004�N��35.8���h���A2005�N52.6���h���A�Ə����ɐL�тčs���A2008�N�ɂ�72.1���h���ƁA4�N�ԂŖ�2�{�ɂȂ�A�ꌩ���̐����͖��̂Ȃ��l�ł���B�Ƃ��낪�AGoogle�̔���グ�ɂ��Č��Ă݂�ƁA2004�N�ł�31.9���h����Yahoo���������Ă����ɂ�������炸�A��2005�N�ɂ͖�2�{��61.4���h���ɐ������AYahoo!������B���̌��Google�̔�������͑��������A2008�N�ɂ�218���h����4�N�ԂŖ�7�{�ɂ��B���Ă��āA���̐�����Yahoo!��傫�������Ă���B
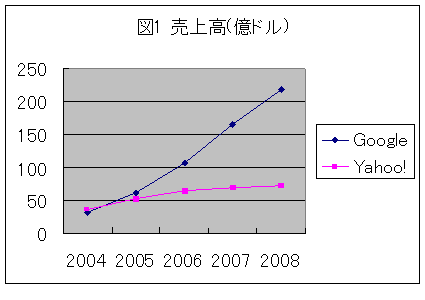
����2004�N�`2008�N�̗��Ђ̏����v�����Ă݂�ƁA���}2�̂悤�ɂȂ�BYahoo!�̏����v��2004�N�̒i�K��8.4���h���A���N�ɂ�2�{�ȏ��19���h�����v�サ�Ă���B�������A2006�N�ȍ~�͉��~�ɓ]���Ă���A2008�N�ɂ�4.2���h���܂ŗ������݁A�Ő�����5����1�̗��v�ƂȂ��Ă��܂����B����AGoogle�̏����v��2004�N��4���h����Yahoo!�̔����ȉ����������A2005�N�ɂ͂����Ȃ�3�{�ȏ��14.7���h���A��2006�N�ɂ����2�{��30.8���h���A������2008�N�ɂ�42.3���h���ƁA����4�N�ŗ��v��10�{�ȏ�܂ŐL���Ă���B�����v�̐L�т̐�����Google�D�ʂ���R�ł���B
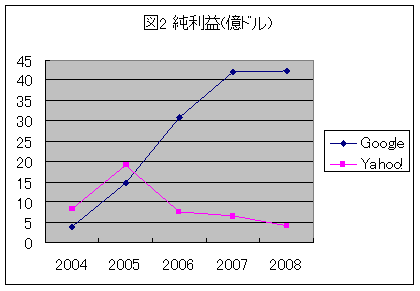
Yahoo!��2008�N3���ɂ͉{���Ґ��ł�Google�Ɏ�ʂ̍���D���A�c�ƕs�U�̐ӔC������Ď��C�����W�F���[�E�������ɂ�������L�������E���o�|�c�В�(2009�N1���A�C)�̉��AMicrosoft�Ƃ̍Č��ɗՂ�ł����B
����AMicrosoft���A���Ƃ��ƃC���^�[�l�b�g���Ɓi�|�[�^���T�C�gMSN�̉^�c�Ȃǁj�Œx����Ƃ��Ă���݂̂Ȃ炸�A�ŋ߂ł͎��v��Ղ̃\�t�g�E�F�A���Ƃł�Google�̐i�o�ɂ��炳��Ă���B���Ђ̋����W���܂Ƃ߂�Ɖ��\�̂悤�ɂȂ�B
�\�@Microsoft�EGoogle�̃T�[�r�X��r�@
| �T�[�r�X���� | Microsoft | |
| �p�\�R���pOS | Windows | Chrome OS |
| �g�ѓd�b�pOS | Windows Mobile | �A���h���C�h |
| Web�u���E�U�[ | Internet Explorer | Chrome |
| �Ɩ��p�\�t�g | Office | Docs |
| �l�b�g���� | Bing | |
| ��v������ | OS | �L�� |
�o��: �w���{�o�ϐV���x2009�N7��9��
�]���̃p�\�R���\�t�g�E�r�W�l�X�̊�{�́AMicrosoft�����p�҂�OS�uWindows�v��Ɩ��p�\�t�g��̔�����ƂƂ��ɁA�O���\�t�g��Ђ�Microsoft�Ƀ��C�Z���X�����x�����������ŋZ�p���A�uWindows�v�����\�t�g��E�̔�����A�Ƃ����d�g�݂ł������B
����ɑ��AGoogle�͐V���ɃN���E�h�R���s���[�e�B���O�̃r�W�l�X���J�n�����BGoogle�͑唼�̃\�t�g�@�\���l�b�g�o�R�ŒA�O���\�t�g��Ђ��\�t�g�@�\���l�b�g�o�R�Œ���BGoogle����������OS�uGoogle Chrome�v�́A�uWindows�v�Ƃ͈���ċZ�p�����Ō��J����I�[�v���\�[�X����������Ă���A�p�\�R�����[�J�[�e�Ђɖ����Œ����B����OS�ł́A�]���^OS�ɔ�ב��쑬�x�E�g������E���S���Ƃ��Ɍ��サ���B���̃N���[��OS�̍ő�̓����́u�l�b�g�𒆐S�ɐv�������Ɓv�ł���B���̂悤�ȁu�l�b�g��p�v�v�Ƃ���VOS�̓����̔w�i�ɂ́A�p�\�R�����l�b�g�o�R�ł̃\�t�g�z�M�p�[���ɓ��������A�N���E�h�R���s���[�e�B���O���y������������_��������B�N���E�h�̕��y�Ńp�\�R�����[�U�[�̃l�b�g���p���Ԃ�����ɑ�����AGoogle�̎��v��9���ȏ���҂��l�b�g�L�������̂�����g��ɂȂ��邩��ł���B
Google�͌g�ь����̖���OS�u�A���h���C�h�v���W�J���ŁA�N���E�h�R���s���[�e�B���O�r�W�l�X�ł͂��́u�A���h���C�h�v�𓋍ڂ��Ă���g�ѓd�b�ɂ��l�b�g�o�R�ő唼�̃\�t�g����邱�ƂɂȂ�A���ꂩ��s�ꂪ�g�傷��ł��낤�B�l�b�g�u�b�N�Ȃǂł́u�A���h���C�h�v�̗��p���\�ɂȂ�B�N���[��OS�ƈꕔ�d�����邪�A�I�����������ق����Z�p�v�V�����܂�₷���Ƃ�Google�l��������B
Google�́A���͍쐬�E�\�v�Z�E�X���C�h�쐬�����ł���Docs�������Œ��Ă���B���܂ŃC���^�[�l�b�g�s���Microsoft��Windows�ɂ��قړƐ肳��Ă��邪�A����Google�̐V���ȃR���s���[�e�B���O�r�W�l�X�́AMicrosoft�ɂƂ��ċ��Ђ̑��݂ƂȂ��Ă���B�@�@�@�@�@�@
2. ��g�̌o�܁E���e
��g�̌o��
��g�̓��e
��g�̊T�v�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
���Ђ��A�i2008�N�̔�����Ď����j�Γ��ȊW�ŁA���T���̃r�W�l�X�����R�ɍs���Ă������Ƃ�]��ł��邱�Ƃ�������B
(�S���F �璼�l, �������)
�͂��߂��@�|�uGoogle vs Yahoo!�v����uGoogle vs MS(&Yahoo!)�v�ց[
Yahoo!�ɐ��Web2.0�Ɉڍs����Google�́A�E�F�u�����s��ɂ����Đ��E�V�F�A�̖�7���Ƃ����m�ł���n�ʂ�z���܂łɂȂ����B�m���ɓ��{�ł̃V�F�A��Yahoo!�ɋy�Ȃ����̂́A���E�V�F�A�ł͈��|�I��ʂƂ������B�����Yahoo!�͐��E�V�F�A�𗎂Ƃ������A���ɒ����̕S�x�ɐ��E�V�F�A�Q�ʂ����鎖�ɂȂ����i�Ē������comScore����2009/8/31�j�B������Yahoo!��Microsoft�i�ȉ�MS�j�Ƃ̋Ɩ���g�ɍ��ӂ��AYahoo!�̌����G���W���ɂ�MS���J������Bing���g�p����邱�ƂƂȂ����B���̂��߁A�E�F�u�����s��ł̋����\���́A�uGoogle vs Yahoo!�v����uGoogle vs MS(&Yahoo!)�v�ւƕω�������B
��L�̂悤�ȋ����\���̕ω��̂Ȃ��ŁA���̐�Google��MS�EYahoo!�A���͂��ꂼ��ǂ��Ȃ��Ă����̂��낤���B������Ƃ̍���ɂ���u���O�v�Ɓu�o�c���j�v�i�������ȉ��܂Ƃ߂āu�Е��v�ƒ�`����j���x�[�X�ɔ�r���A�����̉ۑ�ƓW�]�����Ă����Ƃ��Ƃ���B
���͂̋N�_�@�[�Όڋq�E�ΎЈ�����݂��u�Е��v�̈Ⴂ�[
��q�́u�Е��v�̓��e���A�Όڋq�E�ΎЈ��̊ϓ_����v�Ă݂�Ɖ��\�̂悤�ɂȂ�B
| MS(&Yahoo!) | ||
| �Όڋq | ������ | (��͐��i��) �L���� |
| �ΎЈ� | �l��` | �g�D��` |
�܂���Google�B�u���E�̂���������f�[�^�x�[�X�����A���ł��ǂ��ł��{�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ���v�Ƃ�����]�̉��ɁA�l�X�ȃT�[�r�X���J�����Ă����B�E�F�u�y�[�W�̌����G���W��Google�A�摜����Google Images (GI)�A�n�}����Google Maps (GM)�A�q��ʐ^����Google Earth�iGE�j�A�s�X�n�ʐ^����Google Street View �iGSV�j�Ȃǂ����̗�ł���B�ŋ߂ł́AGmail��Google Appsl�ȂǁA���܂ł�PC��̃A�v���ł����������l�b�g��ŗ��p�ł���A�Ƃ����N���E�h�E�R���s���[�e�B���O�̉\�������[�U�[�Ɍ����n�߂Ă���B�����̃T�[�r�X�͂��ׂāA�l�b�g�ɐڑ��ł�����ł���A�ǂ��ł������Ŏg�p���邱�Ƃ��ł���B���Ȃ킿�AGoogle�̑Όڋq�̊�{���j�̓T�[�r�X�̖����Ƃ�����B�܂��A�ΎЈ��̊�{���j�Ƃ��ẮA�u20�����[���v(=�Ζ����Ԃ�20%�����匤���ɏ[�Ă郋�[��)�ɏے������悤�ɁA�e�Ј��ɂ�肽�����Ƃ���鎩�R�������l��`����������B��K�͉��ɂ�������炸�Ј��̑g�D���͂Ȃ���Ă��Ȃ��̂ł���B
����MS�B�č�IT�ƊE�ő�(�������z�x�[�X)�̒������Ƃł���A���̎�͏��i��Windows OS��Microsoft Office�V���[�Y�ł���BWindows OS�ɂ������Ă͐��E����PC��90%�߂��Ŏg�p����Ă���B�Όڋq�̊�{���j�Ƃ��ẮAWindows OS����͐��i�̗L������������B�܂��A�ΎЈ��̓����Ƃ��ẮA��͐��i�̕ێ�E���ǂ����ɎЈ����g�D������Ă��邱�Ƃ���������B
�ȏォ��AGoogle��MS�͑S���قȂ����u�Е��v�������Ƃ������ł���B���́u�Е��v�̈Ⴂ��O���ɁA���Ђ̎��ƓW�J�Ƃ��̖��_���\�t�g�E�F�A�A���Ќ����̓Ƃ𒆐S�ɔ�r���Ă݂�B
�\�t�g�E�F�A����
������ɐV�����T�[�r�X����Ă���Google�ł��邪�A���̔���̂قƂ�ǑS�Ă��L�������Ɉˑ����Ă���i2008�N�ł�97%�j�B�D�G�Ȑl�ނ����R�X�g�Ōق��Ă��邱�Ƃ�����A2007�N�ɂ̓R�X�g�̏㏸��������̏㏸�����A�Ƃ��������Ԃ��������Ă���B�I�����C���L���ȊO�̐V���Ƃ𐬌������Ȃ���A�R�X�g�ɉ����ׂ���Ă��܂����ꂪ����BGoogle���\�t�g�E�F�A���Ƃɐi�o�����̂��A�iMicrosoft�ւ̑R�S����Ƃ����ʂ�������̂́j�V���ƊJ��ւ̖͍��ߒ��ƌ��邱�Ƃ��ł���BMicrosoft Office�V���[�Y�Ƌ�������Google Docs (2006�N)�AInternet Explorer�Ƌ�������Google Chrome (2007�N)�A����ɂ�Windows�Ƌ�������Chrome OS (2009�N)�̊J���ɂ���āAGoogle��MS�̓\�t�g�E�F�A���ƂŐ��ʂ���Ԃ��邱�ƂɂȂ����B
���̋����W�̍s������q�́u�Е��v��O���Ɍ������Ă݂�B�Όڋq�ʂ���݂�ƁA�uGoogle vs MS�v�́u���� vs �L���v�̋����ɂȂ�A������Google���L���Ȃ悤�Ɍ����邩������Ȃ��B�������A�ΎЈ��ʂ���݂�ƁA�uGoogle vs MS�v�́u��g�D�� vs �g�D���v�̋����Ƃ�������B�g�D�����ꂽ��Ƃ����ǂ����i������Ƃ���A�u��i�� vs ���i���v�̋����ƂȂ�A���ǁA�u����-��i�� vs �L��-���i���v�̍\�}���o���オ��B�Ƃ���AGoogle����������Ƃ͈�T�ɂ͂����Ȃ��B
����AGoogle��MS�̃e���g���[�ɐN�����ė���ɂ�āA�ƑP�I������MS�̑ԓx���ω�������B����܂ł́AGoogle��MS�ɑ��Ă̍U�����ڗ����Ă������A�ŋ߂�Bing��Office�̖����̓�����MS��Google�ɑ��Ĕ����̘T�����グ���ƌ��Ă������BMS�͍��i�����ێ�����Google�̖������i�ɑR���邽�߁A�������L�������i�߂Ă���Ƃ�����B
���Ќ�������
Google Book Search (�ȉ�GBS)�́u���E���̂���������f�[�^�x�[�X������v�ƌ���Google�̖�]��B�����邽�߂̃v���W�F�N�g�̂P�ł���B�����ł́AGBS���ǂ̂悤�ȃT�[�r�X�ł��邩�A���̐��E���̏o�ŎЁA��ƒB�A�����Ďi�@�܂ł����������ޑ���ɂȂ��Ă��܂����̂������Ă������B
Google�͑�w�}���ق�����}���قƒ�g���A�����ŏ��Ђ̃f�W�^������i�߁A���Г��̑S����ΏۂɌ������s�Ȃ����Ƃ��ł���悤�ɂ����BGBS�́A���̓��e�̈ꕔ���͑S�����{���ł���悤�ɂ������̂ł���B�܂�A�l�b�g�ڑ��ł�����ł���A�}���قɍs�����ƂȂ����Ђ�T���ĉ{�����邱�Ƃ��o����Ƃ������̂��B�������Ȃ���AGoogle�����쌠�̗L�����킸���Ђ��f�W�^�����������߁A2005�N�ɑS�č�Ƒg���ƑS�ďo�ŎЋ���u���쌠�ւ̏d��ȐN�Q�v�ȂǂƂ��ďW�c�i�ׂ��N�������B���̍ٔ��͌��ʎ���ŏ��Ђ̏펯���ς��A�Ƒ����̒��ڂ��W�߂Ă����B
����Ȓ��A2008�N10���ɓˑRGoogle�Ƒ��葤�Ƃ̊ԂŘa�������������B���҂̊ԂŘa���Ă�����A2009�N10�����ɂ��o�����A�M�ٔ����̔F��҂��āA�a���Ă͔����Ƃ������ƂɂȂ����B�����ŁA�C�ɂȂ��Ă���̂͘a���Ă̓��e�ł���BITmediaNews���a���Ă̓��e����Ղ��܂Ƃ߂Ă���̂ŁA�ȉ��ň��p���� (http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/25/news089.html)�B
�a���ɂ����Google�́A���N1��5���ȑO�ɏo�ł��ꂽ���Ђ̂����A�č��Ŏs�̂���Ă��Ȃ���ŏ��Ђɂ��āA���p���p���\�ɂȂ�B��̓I�ɂ́i1�j���Ђ��X�L�������ăf�[�^�x�[�X������A�i2�j���Ѓf�[�^��A�N�Z�X����̔�����A�i3�j�e�y�[�W�ɍL����\������\�\�Ƃ��������Ƃ��\���B
Google�́A����œ������v��63����҂Ɏx�����B�����҂ւ̎��v���z�́A�V���ɐݗ������c���c�́u�Ō����W�X�g���v��ʂ��čs���BGoogle�͔Ō����W�X�g���̐ݗ��E�^�c��p�Ƃ���3450���h���i��34���~�j�S����B
�܂��A���N5��5���ȑO��Google�����f�X�L���������S���Ђ̒��쌠�҂ɁA�⏞���Ƃ��đ��z4500���h���i��44���~�j�ȏ��Google���x�����B���Ж{���iGoogle�́u��v��i�v�ƌĂ�ł���j�ɂ��āA�Œ�60�h���������҂Ɏx�����Ƃ��Ă���B
�a���Ă̓��e�́AGoogle�͂�����x�̋��z���x�����Ή��Ƃ��āA��Ŗ{�̏��p���p�̌����邱�Ƃ��o����Ƃ������̂̂悤���BGoogle�͍���̘a���Ă��F�����A�Ɛ�I�ɐ�Ŗ{�̏��Ѓf�[�^���Ǘ����鎖���ł���B�����āA���Ѓf�[�^��̔����̎����o���鎖�悤�ɂȂ�BGoogle�̒n����̂���������f�[�^�x�[�X������Ƃ�����]�̒B���Ɉ���߂Â��킯�ɂȂ�B
�������A�a���Ăɔ�����c�́iOpen Book Alliance�j���ݗ����ꂽ�B���̒c�̂ɂ�Amazon�AMicrosoft�AYahoo!�Ȃǂ̑��n�C�e�N��Ƃ��Q�����Ă���B�ނ�́AGoogle�Ə����̏o�ŎЂ��d�q���Ђ��Ǘ����鎖�ɂ���āA���i�̂�グ��T�[�r�X�̒ቺ�������B�����̗��Q�W�҂ł͂Ȃ�����҂̒����I�ȗ��v���l����ׂ����Ǝ咣���Ă���B����Amazon��Kindle�Ƃ����d�q���Ѓ��[�_�[��̔�����ƂƂ��ɏ��Ѓf�[�^�̔̔����s���Ă���A�d�q���Ўs��Ŋm�ł���n�ʂ�z���n�߂Ă���B�����֍ŋ�Google���V���Ȏ��v����i=�T�[�r�X�����̊�{���j����̒E�p�́j���߂ɓd�q���Ўs��ɎQ������Ɛ����ɔ��\�����B���̂��߁AAmazon�͐��ݓI�Ȍڋq�������Ǝv����Google���Q�����Ă���O�ɁA�X�ɒn�Ղ��ł߂悤�Ƃ��邽�߂̎��ԉ҂����߂ɒc�̂ɎQ�������悤���B����AMS�͈ȑOGoogle�ɑR����ׁuLive Book Search�v�Ƃ����������ƃT�[�r�X��W�J�A�������Ⴂ�����x�䂦�ɓP�ނ����ߋ������BOpen Book Alliance�ł́AGoogle���������邽��Amazon�EYahoo!�Ǝ��g�Ǝv����B
�܂��A�a���Ăɑ��ẮA�uGoogle�ɓƐ�I�ȗ����^���鋰�ꂪ����v�Ƃ��ĕĎi�@�Ȃ��������J�n���Ă����B�����ɗ���Google�́A���쌠�N�Q��肾���łȂ��Ɛ�֎~�@�ɂ��C��z��Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ȃ����B2009�N10��7���ɘa���ď��F�̉ۂ����肷��͂��ł��������A�S���̔������V�����a���Ă̒�o��11��9���Ƃ������߁A�ٔ��͏��Ȃ��Ƃ����Ɛ��J���͑������ƂɂȂ����B
�č��O�̒���ҒB���傫�ȊS�������Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���쌠�Ɋւ���u�x���k���v�̋K��ɂ��A��Google�ƕč��̒���҂Ƃ̑i�ׂł����Ă��a����e�͕č��O�̒���҂ɂƂ��Ă��L���ɂȂ邩��ł���B���̂��߁AEU�̋K�����ǂ��o�ŎЁA��Ɠ���Google�Ƃ̋c�_�ɎQ������悤�ɋ��߂Ă���Ƃ���������B�ŏ��͕č������ł̑i�ז��ł��������A���E�����������ւƔ��W���Ă������B�����āA���Ђ̏펯��傫���ς��Ă��܂���������Ȃ��̂ł���B
Google�̖��_ - �s�f�Ȃ����C�ƒ����̃��X�N
Google�͌����̕����E�F�u��������摜�E�q���ʐ^�E������ЂƍL���A�u���E���̏�������v�Ƃ�����]�𒅎��ɐi�߂Ă���B���̈���ŁA��]�̎����̂��߂ɑ傫�ȃ��X�N��w�������邱�Ƃ������ł���B����́AGoogle���T�[�r�X���������ɁA���[�U�[�̃v���C�o�V�[�Ɋւ���������W�E�Ǘ����邩�炾�B������R�k���Ă��܂�����Google�̐M�p�͎��Ă��A��x�Ɨ�������Ȃ����낤�BGBS�ɂ����Ă͑i�ׂ܂ŋN������A�i�@����Ď������܂łɂȂ��Ă��܂����B
Google�̊�Ɨ��O��1�ɁuDo not be evil�v�Ƃ������̂�����B�u���ɂȂ�ȁv�ƌ����Ӗ��ł��邪�AGBS�ł�Google�̗����U�镑�����͉ʂ����Ď��ł͖����ƌ����邾�낤���H�ŋ�Google�Ɏ��]����MS�ւƈڂ�Ј�����������ƕ����B���������ɂ́AMS����Google�ɂ���ė��Ă܂�MS�ɖ߂�Ƃ����Ј������邻�����BGoogle�ɓ��Ђ������Ǝv���Ă���l���́AGoogle�̎Е����Ɨ��O�Ɋ������ē��Ђ���]���Ă���̂��Ǝv���B�����炱����Ɨ��O�Ȃǂɔ�����悤�Ȏ����s���ƁA���̕��Ј��̎��]�����傫���̂ł͂Ȃ����낤���B�����GBS�̌��ŁA�i�@����̊Ď�����������鎖���\�z�����B����Ȓ��ŁA�uDo not be evil�v�������Ƃ�W�J�ł���̂��낤���HGoogle�͍��A��Ɨϗ��������d�v�Ȏ������}���Ă���Ƃ�����B
GBS�̒��쌠��肩�������������悤�ɁAGoogle�͈�̎��Ƃ̋K�͂����܂�ɑ傫���A���̈��W�J���邾���ő傫�Ȗ�肪�R�ς݂ɂȂ��Ă���B�������z���Ă�������̂������ł���悤�ɂ��Ă����ߒ��ŁA�K�����Ƃ̕������C���N����B���{����������ė~�����Ȃ����̂܂Ō����ł���悤�ɂȂ邩��ł���B�Ί�ƁiMS�j�������Ƃ̐킢���҂��Ă���̂ł���B�܂��������ʂ̑I�ʂɜ��ӓI���삪����AGoogle�ւ̐M�p�͕���B���̑I�ʂ��R���s���[�^�[�ɔC���邽�߁A�V�����R���s���[�^�[�V�X�e�����J������A����𓊂��č�����������V�X�e���p����f�[�^�Z���^�[�̓S�~�Ɖ����Ă��܂��\��������B
�ނ���
�C���^�[�l�b�g���Љ�C���t���ƂȂ��Ă��錻�݁A���Ƃ��i�߂ΐi�ނقǖ�肪�o�Ă��邱�Ƃ��\�z�����B����́A�V�������Ƃ̑������������◘���̒Nj�����A���݂͕�������Ă��邢�����̎s����C���^�[�l�b�g�̃T�C�o�[�X�y�[�X�Ɏ�荞��ł������Ƃł��邩�炾�B�v�͎s��̈ꌳ���ł���B�����ł͑��ƊE�̊�ƂƂ̖��C���N����͓̂��R�ł���B�����āA���̔e����Google, Yahoo, MS�ȂǑ��web��Ƃő����Ă���̂��B�C���t���Ƃ��Ă̈ꌳ���ׂ̈ɂ������̊�Ƃ͂���Ȃ��B�ƂȂ�Ό������������N����͓̂��R�ł���B�܂����̃C���t�����x�������E�K�͂ɂ܂ŗ��Ă��錻�݁A��Ƃ��������m�̃g���u�����Ƃ�Ȃ��̂͑O�q�����ƒʂ肾�B
�C���^�[�l�b�g�ƊE���S���Ă����镔���ƕs�\�ȕ����A��ɓ�����̂Ƃ��̑㏞�A�����𗘕����������ōl���������ł͂Ȃ����낤���B
(�S���F�R�����l, ������)
�~�c�]�v�w�E�F�u�i���_�x�}�����[, 2006�N.
NHK��ޔǁwNHK�X�y�V�����@�O�[�O���v���̏Ռ��x���{�����o�ŋ���, 2007�N.
K.�G���W�F��, ����O�q��w�Ȃ�Yahoo!�͍ŋ��̃u�����h�Ȃ̂��x�p�m�o��, 2003�N.
���X�؏r���w�O�[�O�� �|�����̃r�W�l�X��j��|�x���|�t�H, 2006�N.
���X�؏r���w�l�b�g�����n�}�@�|�|�X�g�E�O�[�O������ 20�̘_�_�|�x���|�t�H,
2007�N.
�|���ꐳ�w�O�[�O�������{��j��xPHP������, 2008�N.
�w���{�o�ϐV���x 2009�N7��9��
�ѐM�s�w�i������O�[�O���x�t�o�Ŏ�, 2009�N.
A.�u���~�X, B.�X�~�X, ���Y����w���t�[�x�O�C��, 2004�N.
�g�����ȁw���t�[�E�W���p���͂Ȃ��g�b�v�𑖂葱����̂��x �\�t�g�o���N�N���G�C�e�B�u, 2006�N.
IT-PLUS�@http://it.nikkei.co.jp/trend/special/interview.aspx?n=MMITzx000027072009
ITMediaNews�@http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/25/news089.htm
IT�p�ꎫ�T�@e-Words http://e-words.jp/
INTERNET Watch�@http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20090709_300880.html
�E�B�L�f�B�A�@http://ja.wikipedia.org/wiki/Wiki
MSN�}�l�[�@http://money.jp.msn.com/
�O�[�O���z�[���y�[�W�@http://www.google.co.jp/�@
CNET Japan�@http://japan.cnet.com/special/story/0,2000056049,20374847,00.htm
TechCrunch Japan http://jp.techcrunch.com/archives/20080411where-are-all-the-google-data-centers/
���t�[�E�W���p���z�[���y�[�W�@http://www.yahoo.co.jp/